介護現場で問題のスピーチロックとは?認知症への影響や利用者への正しい声かけを紹介

スポンサーリンク
目次
介護現場で問題になる「スピーチロック」とは
「スピーチロック」とは、介護者の言葉や声かけによって、高齢者の行動を身体と精神の両方の側面で制限してしまうことを言い、「言葉の拘束」とも呼ばれています。
具体的には「ちょっと待って!」「ダメでしょ!」などの言葉がスピーチロックに該当します。
また、介護者が何気なく使っている言葉や声かけに高齢者が我慢をする、上手く言い返せないことから認知症の進行を助長してしまうことがあります。
そして、スピーチロックには明確な基準や定義がないことから、 一般的な声かけと虐待との違いが分かりにくいとされて、介護現場での問題意識が高まっています。
介護職員による利用者への虐待防止のため、スピーチロックに関する研修や勉強会が注目されています。
スポンサーリンク
なぜスピーチロックは起きてしまうのか
スピーチロックが起こってしまう原因として、介護施設での深刻な人手不足が挙げられます。
人手不足の介護現場では職員1人の業務負担が大きく、介護職員は常に業務に追われています。
介護職員に心の余裕がないことから、利用者1人1人に向き合うことができない。
そのため、介護職員は利用者からの呼びかけに「ちょっと待って!」と返してしまいます。
人手不足が解消されない限り、介護施設でのスピーチロックは解消しにくいと言われています。
しかし、「ちょっと待って」という言葉1つでも、なぜ待つ必要があり、どのくらいの時間待てば良いのか、少し言葉を添えるだけで言葉、声かけの意味合いがガラリと変わります。
また、命令口調では、利用者に対して「動くな!」と言っていると捉えられます。
そのため、介護職員の意識や言葉遣いを少しずつ変えるだけでもスピーチロックの防止・改善には大きな効果を発揮します。
スピーチロックを改善するには、利用者に対して丁寧な口調で、具体的な内容を伝えることが大切です。
スピーチロックは介護現場での拘束で1番見えにくい?
介護現場での身体拘束の定義として、「フィジカルロック」「ドラッグロック」「スピーチロック」の3つがあります。
- フィジカルロック=利用者の身体をベッドに縛るなど、物理的な拘束で動けないようにする
- ドラッグロック=薬物の過剰投与や不適切投与で、利用者の行動を制御する
上記2つの拘束を行うには、拘束具や薬などの道具の用意が必要です。
しかし、スピーチロックは道具の用意もなく、誰でも簡単にできること。
そして「言葉」は目に見えにくいことから、他の2つの拘束よりも起きやすいとされています。
スポンサーリンク
スピーチロックの具体例
具体的にどんな言葉がスピーチロックに該当するのか。
介護職員の言葉やスピーチロックが生じる場面など、スピーチロックの具体例をご紹介します。
介護職員の言葉によるスピーチロック
- 車椅子を使用している利用者が介護職員に「部屋に戻りたい」と声をかけた。
→介護職員は「ちょっと待ってね」と返し、他の利用者の居室誘導でその場を去った。 - 5分前にトイレを済ませ、部屋に戻った認知症の利用者が居室のコールを押し「トイレに行きたい」と言った。
→コール対応をした介護職員は「さっき行ったよ!」とだけ言い残し、居室から立ち去った。
介護職員の態度によるスピーチロック
- 寝たきりの利用者からコールがあり、介護職員が伺うと利用者は言葉を発さなかった。
→コール対応をした介護職員が「何もないなら行くね」と言い、居室から立ち去った。 - 認知症により発語が難しい利用者に介護職員がトイレの声かけを行ったが返答がない。
→利用者の返答がないことにしびれを切らした介護職員が「また後で来ます」と勝手に立ち去った。
スポンサーリンク
スピーチロックでADLが低下したり症状が悪化することも
スピーチロックを行うことで、行動が制限され、必要な動作ができなくなります。
それに伴い、日常で必要な動作ができなくなることや、認知症の症状悪化に繋がります。
スピーチロックがもたらす高齢者への悪影響についてご紹介します。
認知症の進行・症状悪化
認知症では「さっき夕食を食べた」「さっき息子が家に来た」などの短期的な行動の記憶は消えやすく、「怒られた」「無視された」といった感情面での記憶は残りやすいとされています。
そのため、介護職員に「危ないから座って!」と言われると記憶に残ってしまい、介護職員に怒られないようにと無意識的に行動を制限してしまいます。
極端にストレスが加わることで暴力行為や不穏症状に繋がるリスクも高まります。
また、徘徊行為に対して「座っていて」と言われることで「どうして座らないといけないの?」と、かえって本人の混乱を招いてしまいます。
スピーチロックは認知症の方のストレスを高め、症状を悪化させるという認識が必要です。
ADLの低下・介護状態の悪化
スピーチロックでは「部屋に行きたい!」「ご飯が食べたい!」といった利用者の希望を「今は無理!」という一言で禁止してしまいます。
それによって、利用者は意思表示することを諦め、自分から行動することをしなくなります。
その結果、自力でご飯を食べることや、歩くことが困難になるということが起こります。
行動意欲の低下は、筋肉の衰えや関節拘縮などの身体的な悪影響に直結します。
スピーチロックによって筋肉を動かす機会を一気に奪われた高齢者は、食事や入浴、排泄などのADL(日常生活動作)ができなくなってしまい、寝たきり度が高まる恐れがあります。
スポンサーリンク
認知症の高齢者には特にスピーチロックが悪影響を及ぼす
スピーチロックは、認知症の利用者には特に「危険」と言われています。
その理由として、認知症の進行や症状の悪化を招いてしまうリスクがあるからです。
では、具体的にどのような言葉をかけることで、どのような認知症の症状が悪化してしまうリスクがあるのでしょうか。
ここでは、スピーチロックが認知症の利用者に与える悪影響を5つご紹介します。
中核症状が悪化する
中核症状とは、認知症になると必ず現れる症状のことです。認知症の「中核症状」には、以下のような症状があります。
| 記憶障害 | 覚えていたはずのことを忘れる・新しいことが覚えられない |
| 見当識障害(失見当) | 時間・季節・今いる場所が分からなくなる |
| 理解・判断力の低下 | 考えるスピードが遅くなる |
| 実行機能障害 | 計画を立てて買い物や料理などをすることができなくなる |
軽度認知症の利用者は、上記の症状を自覚していることが大半です。
「どうして前までできていたことができなくなったんだろう」「私は最近おかしい」といった不安を感じています。
そのため、介護職が不適切な言葉を使うことで、「無視された」「否定された」という負の感情が強くなり、認知症の中核症状を進行させてしまうのです。
行動・心理症状(周辺症状)が悪化する
行動・心理症状(周辺症状)とは、中核症状が原因で起こる二次症状のことです。周囲の接し方や環境によって、症状の現れ方が異なります。
認知症の「行動・心理症状(周辺症状)」には、以下のような症状があります。
| 徘徊・妄想・幻覚・不安・焦燥感・暴言・暴力・昼夜逆転・食行動異常・抑うつ |
行動・心理症状(周辺症状)の多くは、不安・抑うつ・暴言などの精神的な症状です。
「利用者の失敗を責める」「利用者のプライドを傷つける」「利用者の役割を取り上げる」といった介護職の不適切な対応により、利用者が混乱してしまいます。結果として、「暴言がひどくなった」「徘徊の頻度が高くなった」といった、症状の悪化が見られるようになるのです。
認知症の利用者はストレスにより、不安や抑うつなどの精神疾患が悪化しやすい状態です。介護職は業務に追われて忙しい状況でも、利用者に声をかけられた時はしっかり話を聞き、利用者の不安に寄り添った対応を行うようにしましょう。
行動意欲が低下する
スピーチロックでは、「座ってください!」「やめてください!」など、利用者の行動を制限する言葉が多くあります。1日に何度も介護職から行動を制限する言葉をかけられるうちに、徐々に利用者が自分で動くことを諦めてしまうようになります。
結果として、「自分で歩くことができなくなった」「寝たきり状態になった」など、ADL(日常生活動作)が著しく低下してしまうのです。
強い介護拒否が生じる
認知症の利用者は、周囲の人から「全てわからなくなってしまっている」という勘違いをされてしまいがちです。しかし、認知症の利用者は「言葉が思うように出なくても、耳がしっかり聞こえている」「その時々に感じたことは覚えている」などの残存能力があります。
介護職に「無視された」「否定された」という嫌悪感・不快感・恐怖心などは記憶に残っているため、強い介護拒否をするようになるのです。強い介護拒否が生じると、安全に介護を行うことが困難になってしまい、介護職側も利用者の対応に頭を抱える事態になってしまいます。
介護施設での生活が困難になる
介護職が継続的にスピーチロックとなる言葉をかけ続けることで、利用者は不安や恐怖心が日に日に増していきます。強い介護拒否が生じ、どの介護職でも手に負えない状態まで認知症が悪化してしまうと、やむを得ず利用者に退去を命じることになるケースがあります。
入居していた介護施設から他の介護施設や医療機関へ移ったり、場合によっては家族が在宅介護を受け入れることになるのです。利用者本人とご家族、他の介護施設や医療機関など、様々な人に負担がかかるため、日頃から不適切ケアの撲滅に取り組む必要があります。
スポンサーリンク
スピーチロックの対策方法は?
利用者への声かけ、言葉かけはコミュニケーションの一環です。
人手不足の介護現場では、職員の多忙が理由でコミュニケーションを省いてしまうことが大きな原因となり、短く強い言葉で利用者に職員の意思を伝えてしまいます。
利用者を尊重したコミュニケーションこそがスピーチロックへの対策です。
スピーチロックの防止・改善に向けた具体的な対策方法についてご紹介します。
介護職員の行動傾向を自己覚知する
- 自分自身が業務に追われて利用者の呼びかけにすぐ対応できない時。
→それはどんな時間帯で、どんな業務内容の時が多いか。 - 利用者に対して強い言い回しや命令口調になってしまう時がある。
→それはどんな状況の時で、それ以外の状況ではどんな声かけをしているか。
このように、自分自身の行動の傾向について、まずは考えてみることが大切です。
普段から自身の行動を自覚・把握することが、無意識的なスピーチロックの防止に繋がります。
否定せず、相手の気持ちを考える
「~しないで!」といった否定は利用者の行動を止めるだけでなく、心を傷つけてしまいます。
利用者に話しかける前に、数秒間だけでも「なぜこの人はこれがしたいと言っているのか」という利用者の気持ちについて一旦考える時間を作りましょう。
利用者の気持ちを考えることで、「それなら、~をしていただけますか?」 といった、代替案の提示や依頼が可能になります。
提示や依頼を受ければ、利用者も「じゃあそうしようか」と行動を選択できます。
また、利用者に対して思いやりやマナーを守った言葉遣いをすることも大切です。
利用者の気持ちを尊重しつつも、介護職員の要望を伝えるためにも「~してくれる?」といった上から目線の言葉は好ましくありません。
伝える内容はもちろん、言い方を丁寧にするだけでもスピーチロックの改善に繋がります。
スポンサーリンク
スピーチロックを防ぐ言葉の言い換えを覚えておこう
スピーチロックを多忙を極める介護現場では、意図せずにふと、利用者が「威圧的」「乱暴」と感じるような言葉遣いをしてしまう時があります。
スピーチロックとして利用者の行動を制限してしまわないよう、日頃から言い換えの言葉を用意しておくことが大切です。
スピーチロックを防ぐための言い換え言葉の例文集をご紹介します。
スピーチロックを防ぐ言い替え言葉の例文集
| 不適切な声かけ (スピーチロック) | 言い換え例 |
| 「ダメですよ」 「やめてください」 | 「○○さん、どうされましたか?」 「ベッドから落ちてしまいますので、やめて頂けますか?」 「怪我をしてしまうので、○○(他のこと)をしませんか?」 |
| 「早くしてください」 | 「急がなくても大丈夫ですよ」 |
| 「さっきも同じこと言いましたよ」 | 何度同じことを尋ねられても、その都度笑顔で受け答えする |
| 「そこにいてください」 | 「どちらに行かれるんですか?」 「私もご一緒させて頂きたいので、あと5分待って頂けますか?」 |
| 「座ってください」 「立たないでください」 | 「どこか行かれますか?」 「立っているとふらつきませんか?よかったらこちらに座ってください」 |
| 「ちょっと待ってください」 | 「〜を終えてからすぐに伺いますので、5分ほどお待ちください」 「今洗濯物を取り込んでいるので、あと3分待っていただけますか?」 |
| 「なんでこんなことをしたんですか?」 | 「どうされたんですか?」 「なにかあったんですか?」 |
| 「危ないですよ」 | 「お1人だと危ないので、私もご一緒してよろしいですか?」 |
| 「家には帰れませんよ」 「今日は泊まりですよ」 | 「帰る時間になったらお伝えしますね」 |
| 「まだ寝ててください」 「まだ起きる時間じゃないですよ」 | 「今はまだ朝の10時ですよ。12時に昼食が用意できるので、その時に起きませんか?」 |
| 「食べてください」 | 「もう少し食べてみませんか?サワラとお野菜のあんかけ、どっちが食べたいですか?」 |
言い換えの言葉は、上記以外にもたくさんあります。
スピーチロックの言い換えについて上司や同僚と話し合い、思いついた言葉を一覧表に書くようにすることをオススメします。また、作成した一覧表は常に確認できるよう、掲示・携帯したり、日頃から研修や勉強会を行い、職場全体で共有しておくことで、不適切な言葉をうっかり使ってしまうことが防げるでしょう。
スピーチロックの言い換え言葉のポイントは、以下の3つです。
- 否定ではなく、「~していただけますか?」とお願いする言い方にする
- 「今は~をしているので、あと5分待っていただけますか?」と、時間や介護職の考えを具体的に伝える
- 「どうしましたか?」と優しい口調で利用者の考えを尋ねる
言葉遣いや声のトーンを少し変えるだけで、利用者に不安や恐怖心を与えることなく介護職の思いを伝えることができます。
利用者の行動を「ダメ!」「やめて!」と止めるのではなく、「どうされましたか?」と伺うことで、利用者の行動の目的を知ることができるのです。
言葉遣いや声のトーンを工夫しながら、利用者に寄り添った対応を行うことが重要です。
スポンサーリンク
ふとした一言が相手の行動を制限しているかも
介護現場では介護職員の人手不足により、職員1人当たりの業務負担量が多くなります。
つい、業務に追われてバタバタしている時は利用者に対して声かけがいい加減になりがちです。
しかし、それこそがスピーチロックが起きてしまう最大の要因です。
利用者を心身共に拘束し、介護状態や認知症の悪化を招かぬよう、介護職員は常に利用者へ丁寧に接することが求められます。
そのためには、自分の行動傾向について自覚し、悪い言葉の言い換えを用意しておくなど、普段からスピーチロックについての意識を高めておくことが大切です。
適切な判断と対策で介護現場からスピーチロックを完全になくすことを目指しましょう!
Related Posts

記事を探す
CLOSE



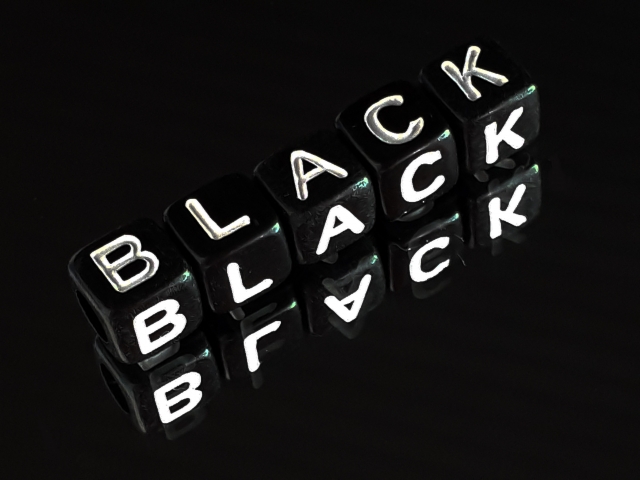
 カテゴリから探す
カテゴリから探す カテゴリから探す
カテゴリから探す